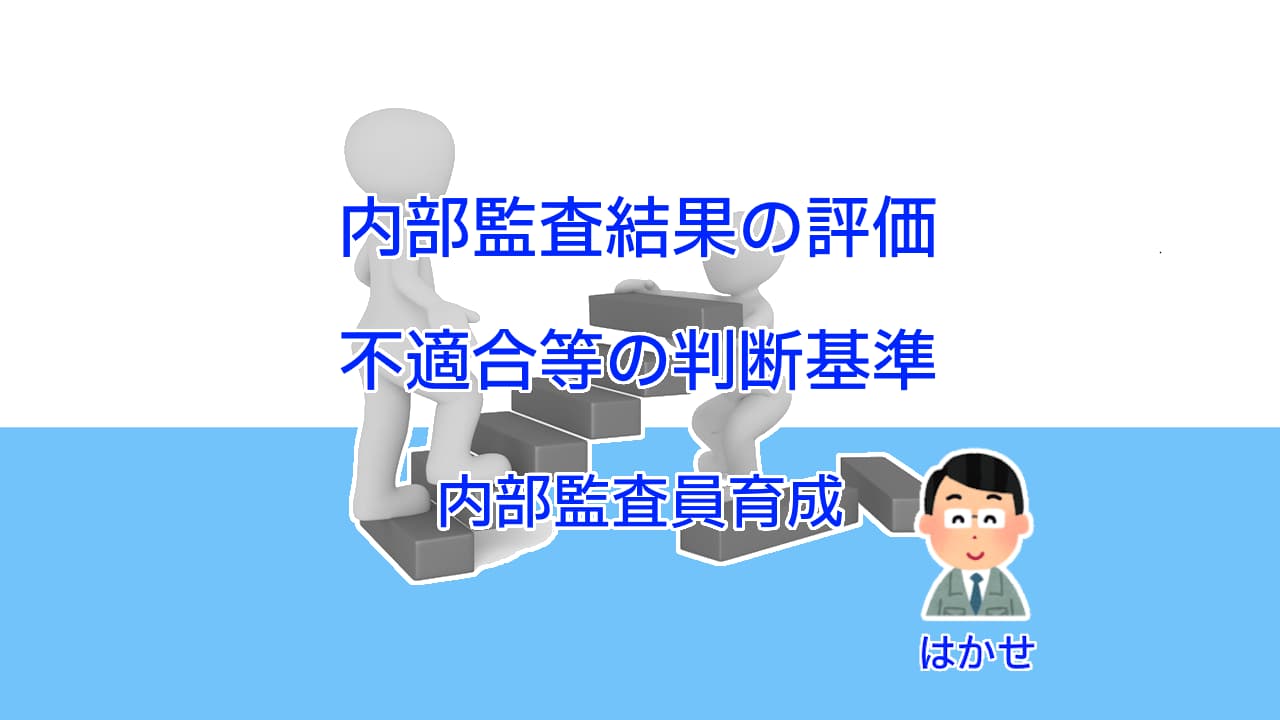「内部監査規定(リンク先はこのブログの内部監査規定です)」と内部監査ガイドを使って、内部監査についての教育をはじめます。
- 内部監査ガイドは、Amazon Kindle:「ISO内部監査の取扱説明書」、このブログでは「内部監査ガイド」のページにまとめています。
内部監査は、不適合や観察事項を指摘するために行うわけではありませんが、内部監査員は、不適合や観察事項と判断するための基準を意識していることが必要です。
ここでは、内部監査員(リーダー、メンバー)が、不適合や観察事項とする判断基準について教育します。
内部監査員育成の登場人物を簡単に紹介します。

内部監査責任者の「はかせ」。社内ではISOの人といわれるtこともありますが、博士(工学)でもあります。
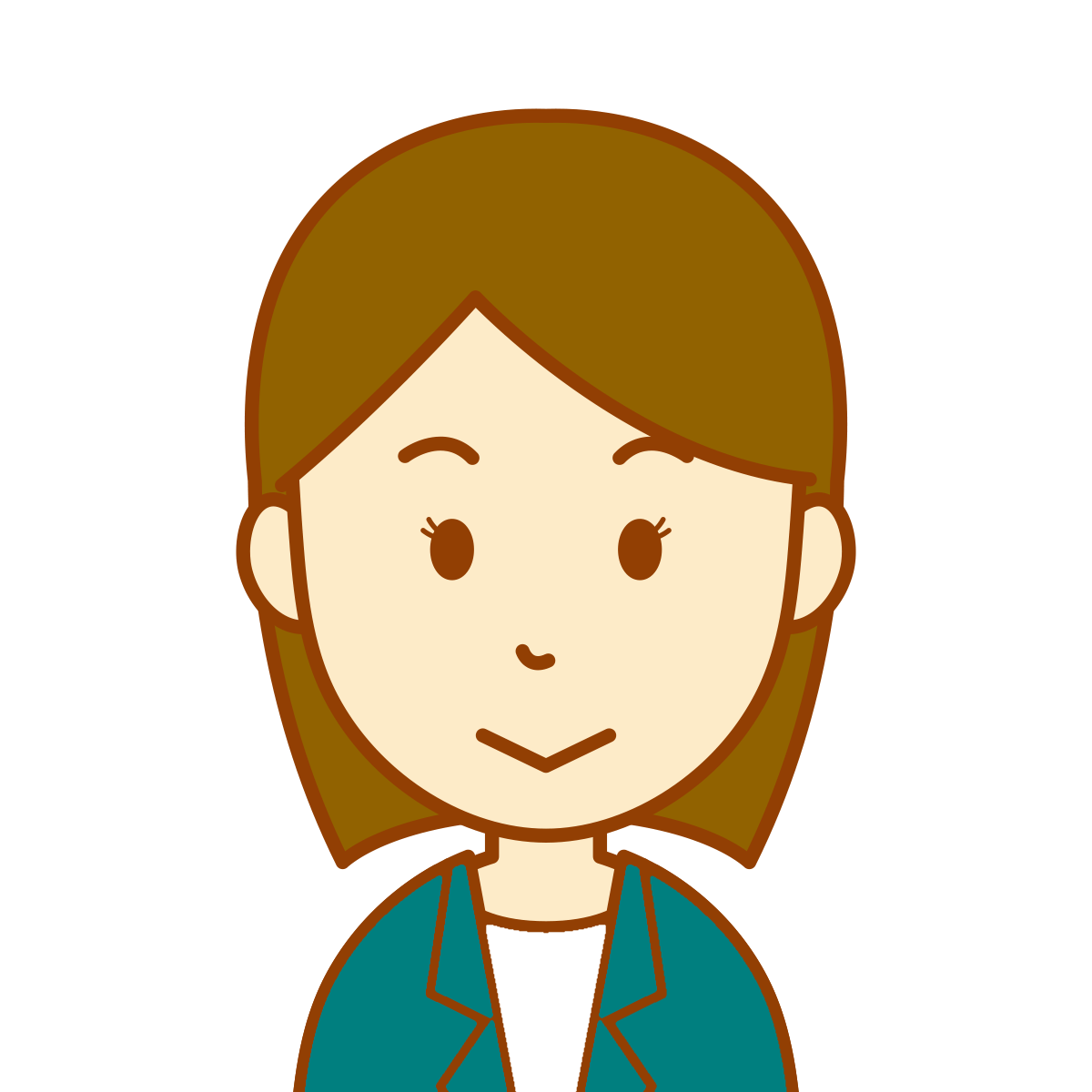
社会人経験は浅いものの知らないことにも前向きに取り組む「レイ」さん。上司から推薦された内部監査候補者。
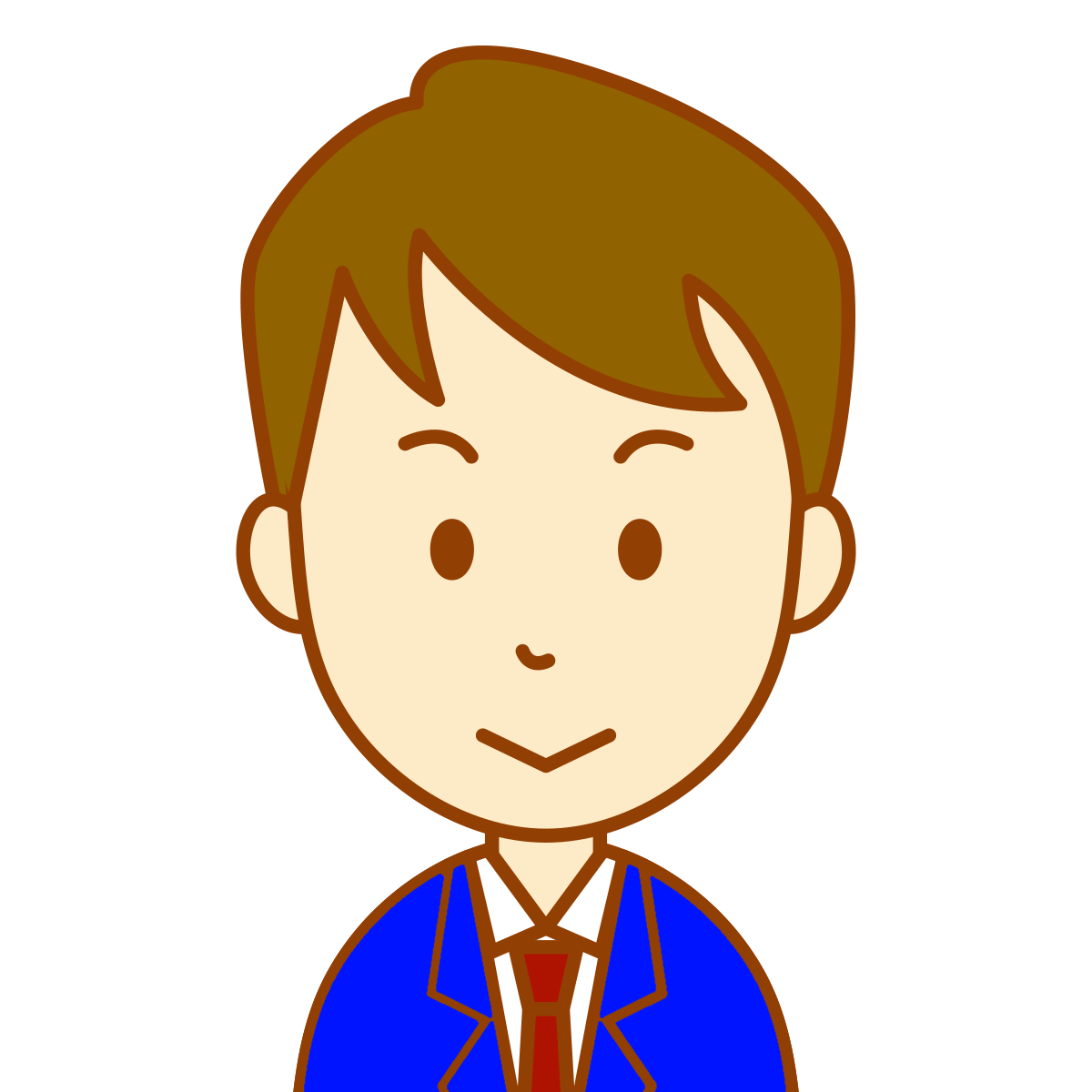
社会人経験の浅いレイさんと同期の「ソラ」さん。途中から内部監査員教育に参加予定です。
内部監査で指摘することが目的になりがちな理由
内部監査の目的を「業務改善に役立つこと」にしていても、内部監査員(リーダー、メンバー)は、無意識のうちに不適合や観察事項を探すために質問したり観察したりしてしまいがちです。
記録が無かった場合を例にすると、内部監査チーム内では次のようなやりとりになりがちです。
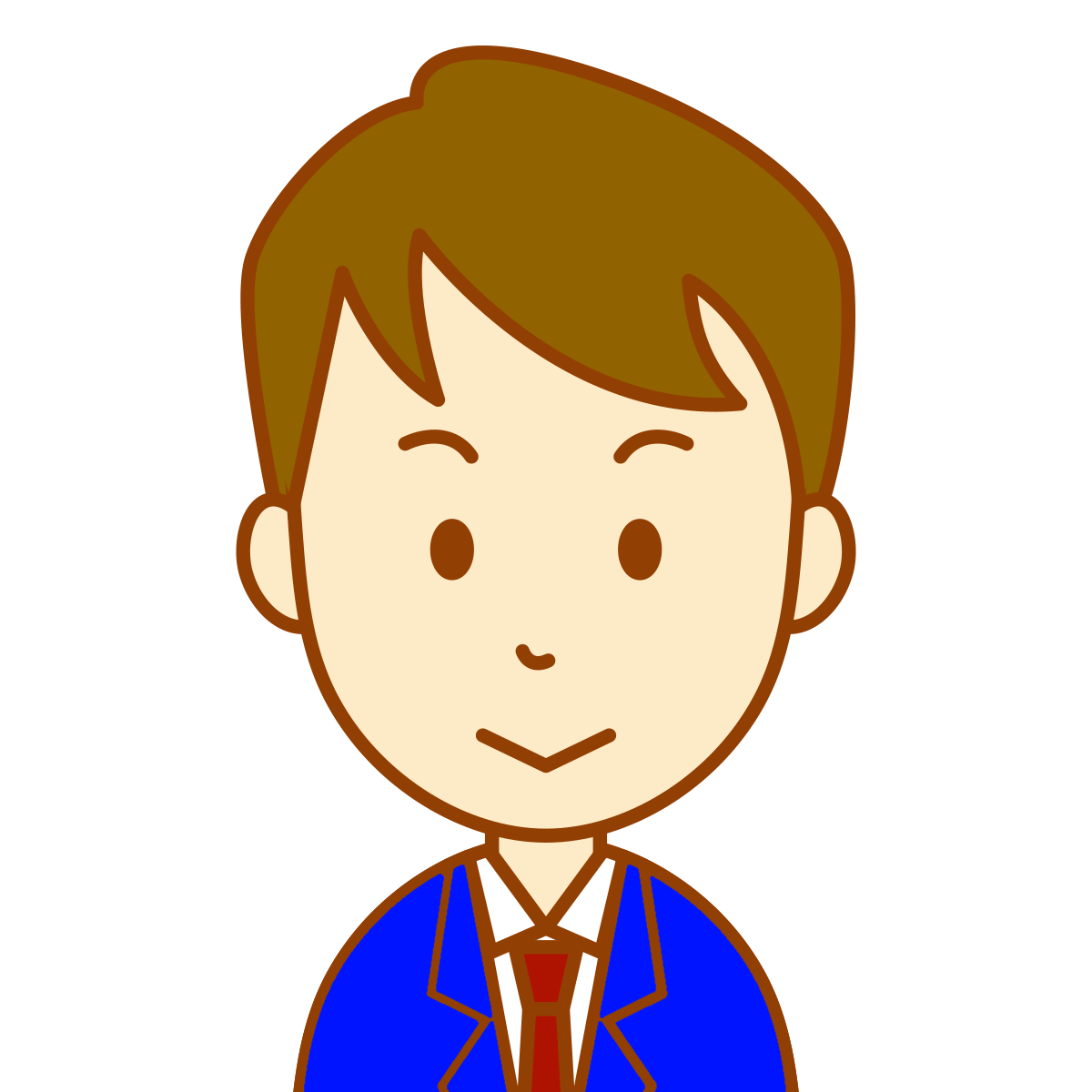
記録が無いので、不適合ですね。

記録が無い理由は何ですか?
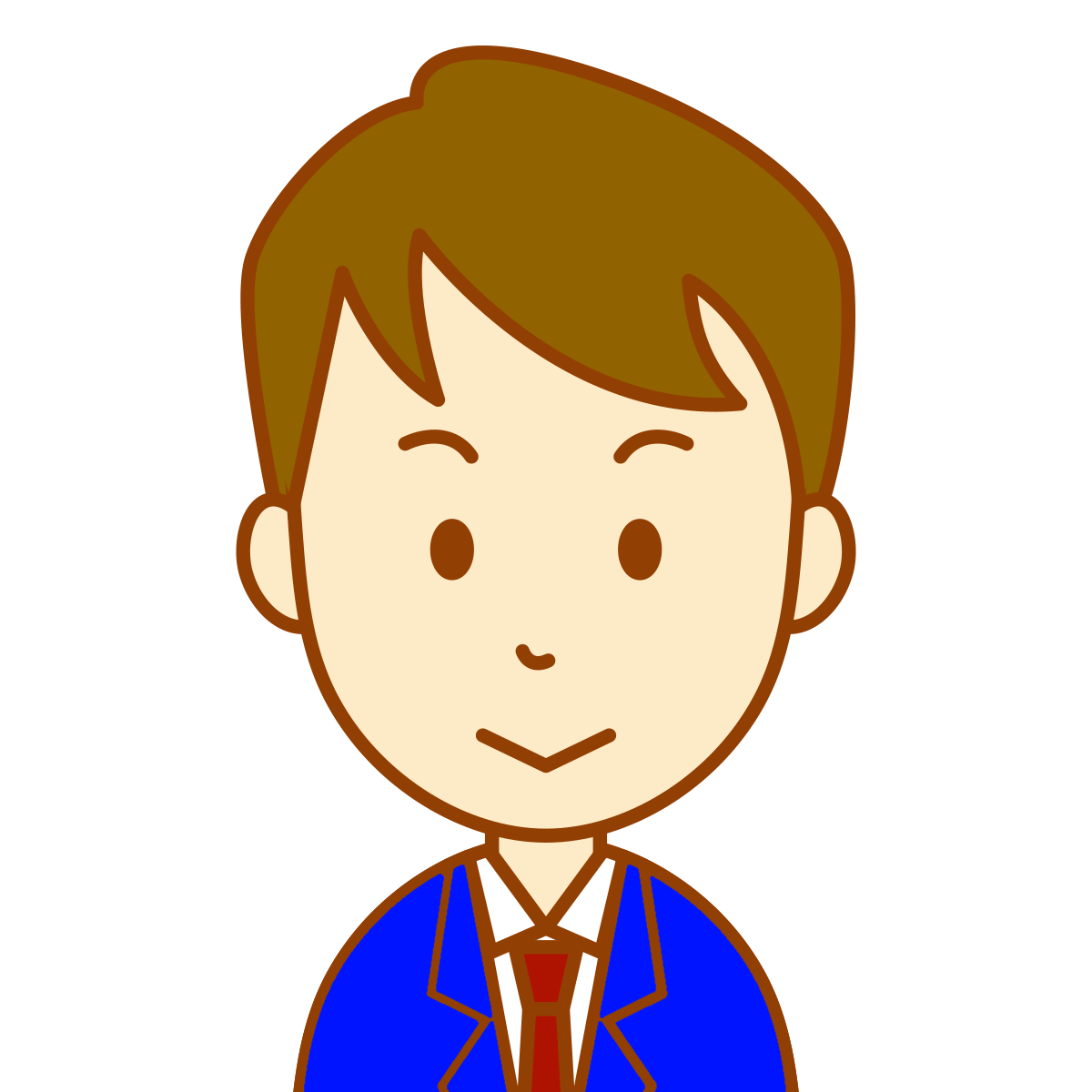
規定に定められた記録がないから、不適合となるのではないのですか?

内部監査の目的を思い出してください。
何のために内部監査をしていますか?
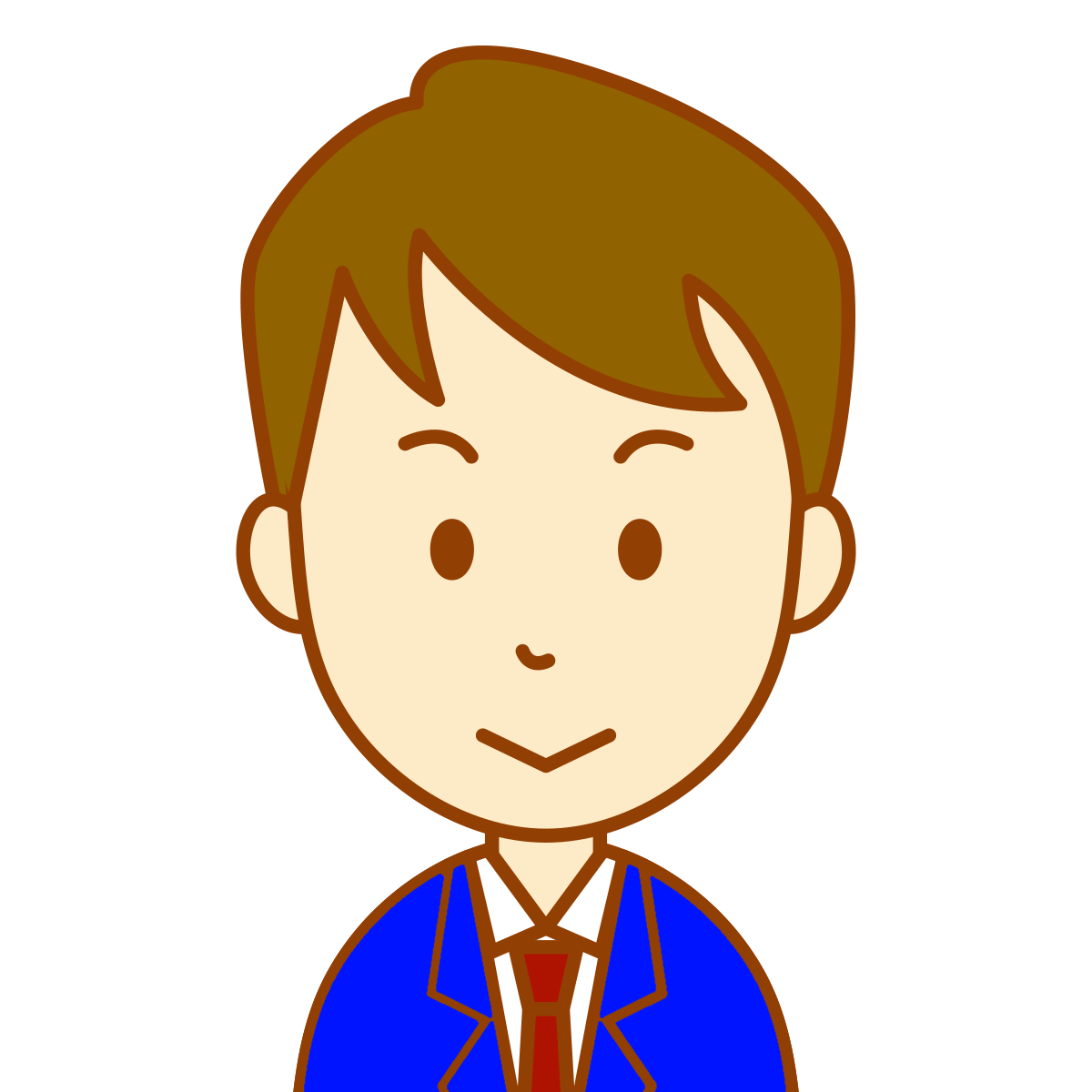
業務改善につながることや困っていることなどがないかを確認することだと教えられました。

記録が無い理由にもいろいろあります。
「たまたま忘れてた」こともあれば、「記録を使っていない、あるいは、不要なので残していない」ような場合もあります。
内部監査員としては、必要な記録であれば忘れないようにするにはどうするか、記録が不要なのであれば規定を見直すのかなど、視野を広げて記録が無い理由をみつけることがポイントです。
なぜ、このような指摘になってしまうのでしょうか?
記録が無いから不適合や観察事項だと短絡的に判断してしまう場合、その対応(教育)は簡単ではありません。
不適合だと判断した当人は、自分では監査対象部署の業務改善につながる(約にたつ)と思いんでいるため、内部監査の目的を再度説明して、不適合とすることで本当に業務改善につながるのかや、記録の無い理由を確認したのかなどを説明したりして、自分の判断が短絡的になっていないか確認してもらうようにしています。
また、できていないことをみつける方が、できていることをみつけるよりも容易に思われていることも理由の1つだと考えています。
内部監査員のリーダーとメンバーは、不適合や観察事項だと判断したことが、互いの立場でどう思うか、監査対象部署の業務改善につながるかどうかを確認しあうだけでも、思い込みに気づきやすくなります。
内部監査の基準
内部監査の基準は、内部監査規定に明示されている通りです。
不適合と観察事項の判断基準について説明します。
重大な不適合と軽微な不適合
内部監査で実際に不適合かどうか判断が必要になるのは、軽微な不適合、例えば、
- 規定で定められた手順と実態(実施内容)の一部に不整合がある。
- いわゆるヒューマンエラー
の場合などです。
重大な不適合とは、次のような場合であり、通常はありえないと考えています。
- 品質マネジメントシステムの必要なプロセスが欠落している。
- 繰り返し起きているのに放置されている。
- 規定などのルールを全く無視している。
観察事項
観察事項とは、
- そのまま放置しておくと、将来的に不適合となる恐れのあること
です。
さらに、内部監査員としては、
- 観察事項で指摘したことを、監査対象部署で改善できることであるか。
についても配慮が必要です。
不適合や観察事項の考え方の例
例えば、あるべき記録が無い場合を例にすると、
- ヒューマンエラー(たまたまその記録が無かった場合など)
- 規定と実務との不整合がある場合
には、観察事項とすることで、
- ヒューマンエラーは、発生を防げないヒューマンエラーに対して、やり方に変更したりして、再発防止をする。
- 規定の見直しををする。
といったことができることがポイントです。
監査リーダーが規定の見直しが必要だと判断した場合、次のような対応が考えられます。
- 監査リーダーは、規定の見直しは監査対象部署の問題ではないため、不適合や観察事項とはせず、規定と実務との不整合があったことをチェックリスト等に残し、監査責任者に報告します。
- 監査責任者は、規定と実務の不整合があり、規定見直しの必要があることをISO管理責任者に報告します。
- ISO管理責任者は、別途、規定見直しを進める。
内部監査結果の報告
内部監査の結果は、監査リーダーは、監査責任者に報告します。
- 内部監査報告書
- チェックリスト(内部監査報告書のエビデンスとしての役割もあります。)
監査責任者は、個々の内部監査報告書(チェックリスト等を含む)を確認し、内部監査報告書(総括)を作成し、ISO管理責任者に報告します。
また、不適合や観察事項については、適時フォローします。
ISO管理責任者は、内部監査報告書(総括)に、不適合や観察事項のフォローアップ結果を含めマネジメントレビューのインプット情報とします。
また、必要に応じ、社長に報告します。
まとめ
「内部監査規定(リンク先はこのブログの内部監査規定です)」と内部監査ガイドを使って、内部監査についての教育をはじめました。
内部監査は、不適合や観察事項を指摘するために行うわけではありませんが、内部監査員は、不適合や観察事項と判断するための基準を意識していることが必要です。
ここでは、内部監査員(リーダー、メンバー)が、不適合や観察事項とする判断基準について、以下の項目で説明しました。
- 内部監査で指摘することが目的になりがちな理由
- 内部監査の基準
- 重大な不適合と軽微な不適合
- 観察事項
- 不適合や観察事項の考え方の例
- 内部監査結果の報告