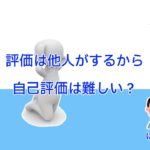評価とは、評価基準(物差し)に対しどのレベルにあるかを判断することです。
- ここでいう物差しとは、評価基準のことです。
-
例えば、3段階評価なら、ABC、◯×△などの3段階で評価する基準のことです。
評価する目的や評価基準が明確であっても、実際に評価すること(どのレベルにあるか判断すること)は簡単ではないと考えています。
ここでは、これまで内部監査員や職場での教育の場で話したり、人事評価(考課)の際に説明したり、あるいは、雑談の様な相談の中で話してきた、評価や物差しについて説明します。
評価とは
まず評価について、説明します。
評価は、評価される人とは別の人がするものです。

自分でする評価は、自己評価です。自己評価も評価の1つではありますが、特別な評価だと考えています。
評価をするには、基準となる物差しが必要になります。
会社での人事評価(考課)であれば、評価の仕方に評価項目や評価基準などが文書化されていると思いますが、その場合でも、どの様な理由でその評価になったのかが問題になることもあります。

評価は気にしても変わらないので気にしないまま半世紀以上仕事をしてきました。
給料に直結する人事評価で納得したのは上がったときだけだったかと。評価に納得できるのは、貴重な体験なのかもしれないですね。
自分の物差しとは
自分の物差しについて説明します。
こんな経験はないでしょうか?
- 入社してある程度経験してはじめて気づく、入社した会社の常識(物差し)について違和感を感じたことはありませんか?
- 例えば、(自分が思っている、イメージをもっている)社会の常識と会社の常識にずれがあると感じたことはないでしょうか?
新卒、中途を問わず、入社した社員への自部署の紹介の際には、次のようなことを伝えています。

「自分の物差しを大切にしてください。」

「自分の常識と会社の常識とが違うのは、物差しが違うからです。この時、会社の物差しにあわせるのではなく、自分の物差しと会社の物差しとの違い(差)を意識するようにしてください。」
その理由は、自分の物差しと違うと感じている会社の物差しになれてしまい、自分の物差しと会社の物差しが同じになってしまうと、入社当初に感じることができていた差を感じることができなくなってしまうからです。
自分の物差しをもっていれば、他の人の物差しと比べることができます。

例えば、会社に染まって自分の物差しがなくなってしまうと、会社の外に出た時に困ったことになると考えています。
内部監査での評価について
内部監査での評価について説明します。
内部監査員責任者として行う評価は、すべての内部監査報告書を提出し、不適合がある場合は暫定処置が終わってから、すべての内部監査員の評価をしています。
内部監査員の評価をする場合、以下の結果を判断材料にしています。
- 部署の品質目標計画と進捗管理(報告書とチェックリスト)
- メンバーの力量と教育・訓練結果
この際、評価に必要な物差しは、次のように1つではありません。
例えば、内部監査の判断や評価の物差しにもいくつかあります。
- 監査対象部署の部署長としての物差し
- 内部監査員としての物差し
- 個人の物差し
上述の3つの物差しは絶対評価の物差し(基準)ではないことに注意が必要です。
自分の物差しがあれば、次のことが分かります。
- 自分自身と内部監査員の判断・評価基準の違い。
- 内部監査員と部署長の評価・判断基準の違い。
自己評価
評価には様々なものがありますが、自己評価はとても難しいと感じています。
自己評価が苦手だという話は聞いても、自己評価が得意な人に出会うことはスペシャルなコンサルタントやカウンセラーぐらいではないかと思っています。
自己評価が難しいと思う理由は、客観性を保つのが難しいからです。
うっかりすると自己評価をしていたはずが、いつのまにかに自己嫌悪の状態になってしまい、「はて何をしようとしていたのだろう?」と我にかえることさえあります。
自己評価は、自分で行う評価です。
自己評価の相対評価というのはイメージしがたいですし、他者が行う評価でもないので、自分の物差しによる絶対評価と考えられます。
自己評価が絶対評価だとすると、自分の物差しが絶対評価に対応できることが必要になります。
評価の思い出
仕事にまつわる評価に関する思い出をいくつか紹介します。
評価は難しいなと私が考える理由の説明になるかもしれません。
公務員の時
先輩から、「面識もなく名前さえ知らない方が「全然分かってないと」言っていたけど、何をしたんだ?」と聞かれたことがあります。
「他人の評価だから仕方ないですよね。」と答え、「それはそうだけど・・・。」で終わりました。
商品企画担当の時
開発案件の企画段階で、「社歴の長いAさんは無理だと言っている。」と商品企画の担当役員に聞かされたことがあります。
最終的にその企画は商品となったのですが、どのような理由でそのようなことを言われたのか個人的な興味はありましたが、聞いたところで何も変わらないだろうと思い、気にしないことにしました。
人事評価で給料が上がった
確か情シスのマネージャーだった時、1度だけ3段階評価のBをもらって給料が上がったことがありました。
「あのメンバーでこれだけのことをやってますけど、どうなんですかね。」と、上長に丁寧にお話しした覚えがあります。
評価制度が整備されていても、実際の運用(判断)には疑問をもつこともありますが、人が判断することなのでそういうものなのだろうと考えていました。
モノづくり会社の時
上司に呼び出され、「Aさんが当たりが強い。」と言ってるけれどと聞かれたことがあります。
「もう1年ぐらい仕事を頼んでいませんけれど。仕事が減ってることに気づいてないんですかね。」と答えた覚えがあります。
「同じポジションのBさんは、仕事を取りに行ってこなすから、Aさん同様ミスはありますが、仕事を頼めるんですよね。」とは心の中のつぶやきでした。
まとめ
評価とは、評価基準(物差し)に対しどのレベルにあるかを判断することです。
評価する目的や評価基準が明確であっても、実際に評価すること(どのレベルにあるか判断すること)は簡単ではないと考えています。
ここでは、これまで内部監査員や職場での教育の場で話したり、人事評価(考課)の際に説明したり、あるいは、雑談の様な相談の中で話してきた、評価や物差しについて、以下の項目で説明しました。
- 評価とは
- 自分の物差しとは
- 内部監査での評価について
- 自己評価
- 評価の思い出
- 公務員の時
- 商品企画担当の時
- 人事評価で給料が上がった
- モノづくり会社の時

内部監査責任者として、内部監査員の力量評価は毎年やっていますが、教えるのは難しそうです。
会社員としては報酬に直結する人事考課は気になりますが、最終的に社長判断となる運用の場合、目標管理などの評価は意味があるものなのか疑問に思うこともあるので、経営層になると評価の難易度が跳ね上がるのかもしれません。