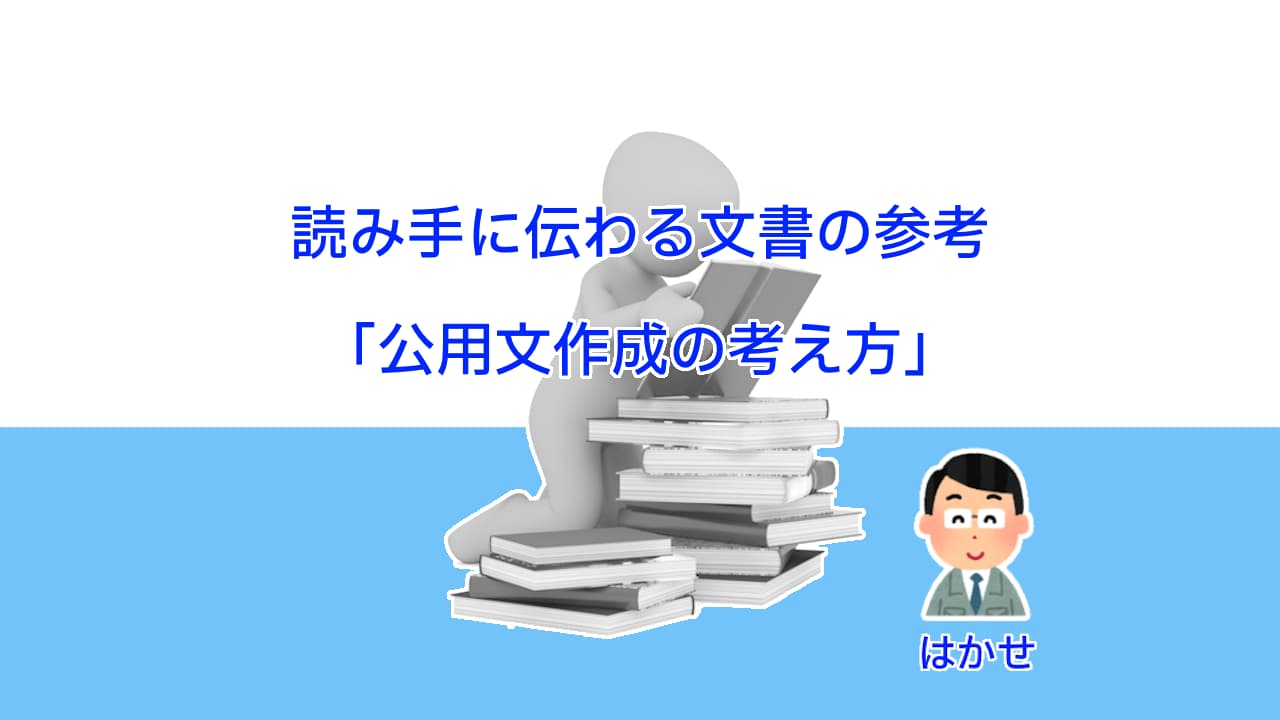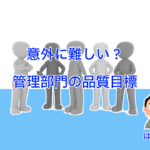品質マニュアルや関連規定を作ったり見直したりする時に、章立てや書式、文言の使い方や表記ゆれに悩むことがあります。
ISO9001やISO14001などのマネジメントシステムの要求事項は、「MSS共通テキスト」により、章立てを共通化していますので、品質マニュアルや環境マニュアルは、ある程度形ができています。
しかし、そのまま規定類にも適用するかというと、社内文書との違いもあり、簡単な作業ではありません。
実際、品質マニュアルと関連規定の維持管理をしていると、中身ではなく体裁について気になることが出てきます。
- 例えば、表記ゆれ、気になると肝心のマニュアルや規定等の作成が中断します。
- かといって無視すると、形になってから後悔することになります。
ここでは、実際に使える参考資料として、お役所ですが文化庁の「「公用文作成の考え方」について(建議)」について説明します。
品質マニュアルや規定類の書式や文書としての整合性
品質マニュアルと関連規定類の文書としての整合性は最初が重用なのですが、現実問題として、最初から書式や文書としての整合性を自社にあわせてきっちり決めて作ることは難しいようです。
ISO9001の認証取得を例に、文書の整合性に注目して時系列での1例を説明します。
認証取得前後
認証取得時は、要求事項を満たすマニュアルと規定類を作ることが最優先です。
品質マニュアルは、要求事項と同じ章立てになるので、QMS体系図を作るのは少々時間がかかりますが、マニュアルは1つだけなの形にはしやすいです。
しかし、営業、技術、製造などの部門間でも各々関連規定類については、規定類の文書レビューや内部監査などの結果を受けて改訂が繰り返されます。
この時の改訂における文書としての整合性は、営業、技術、製造などの部門内に限られがちです。
3年後(1回目の更新審査後)
1回目の更新審査が終わる頃、品質マニュアルや関連規定類、全体の文書としての整合性が気になりだします。
文書管理規定や関連標準には、規定類の文書としての体裁や整合性は最低限の表現しかしていないことが多いと思います。
規定類の改訂時の文書レビューや内部監査でも、不適合にする事象ではないし、実際に改善するとなるとかなり大変な作業になることに気づきます。
規定類の文書としての整合性は、
- 表記ゆれは、言葉の定義の課題
- 各部門間の整合性は、複数部門間の課題
に関連します。
例えば、表記ゆれを修正する場合、品質マニュアルは、最上位文書なので何とかできます。
しかし、各規定類は、実務で使われる言葉で説明するので、1つの単語が一般的な意味と違う場合もあれば、各部門で意味が違う場合もあります。

言葉ときちんと意識して、使い分けして仕事が進んでいるなら、それは優れている点であると評価しています。
そこで、まずは、各部門内で改訂を進められる規定類の表記ゆれや文書としての整合性をとるようにします。
なお、表記ゆれや文書としての整合性について、「どこまでやるか」を決めるのは、「何のためにやるか」です。

文書の「表記ゆれを無くすこと」や各規定類の「文書としての整合性を無くすこと」が目的とならないように注意します。
「「公用文作成の考え方」について(建議)」について
文化庁から
「「公用文作成の考え方」について(建議)」
が公開されています。
- 「建議」は「意見書」と「建議した」は「提案した」考えればよさそうです。
- 2022年1月7日(令和4年1月7日)に公開されています。

「公用文改善の趣旨徹底について」1952年4月4日(昭和27年4月4日)が廃止されていますので、実に70年前のルールで公用文を作っていた?ことになりそうです。
IT後進国どころの話ではなく、別世界での話に聞こえます。
公用文とは、法令や告示・通知等のお役所の文書のことですが、読む人に伝わる文章を書くための参考になりましたので、紹介します。
「公用文作成の考え方」について(建議)」の目次
以下、「公用文作成の考え方」について(建議)」の目次を紹介します。
基本的な考え方は、公用文以外にも共通する内容です。
基本的な考え方
1 公用文作成の在り方
1-1 読み手とのコミュニケーションとして捉える
1-2 文書の目的や種類に応じて考える(表「公用文の分類例」参照)
2 読み手に伝わる公用文作成の条件
2-1 正確に書く
2-2 分かりやすく書く
2-3 気持ちに配慮して書く
Ⅰ 表記の原則
1 漢字の使い方
2 送り仮名の付け方
3 外来語の表記
4 数字を使う際は、次の点に留意する
5 符号を使う際は、次の点に留意する
5-1 句読点や括弧の使い方
5-2 様々な符号の使い方
6 そのほか、次の点に留意する
Ⅱ 用語の使い方
1 法令・公用文に特有の用語は適切に使用し、必要に応じて言い換える
2 専門用語は、語の性質や使う場面に応じて、次のように対応する
3 外来語は、語の性質や使う場面に応じて、次のように対応する
4 専門用語や外来語の説明に当たっては、次の点に留意する
5 紛らわしい言葉を用いないよう、次の点に留意する
6 文書の目的、媒体に応じた言葉を用いる
7 読み手に違和感や不快感を与えない言葉を使う
8 そのほか、次の点に留意する
Ⅲ 伝わる公用文のために
1 文体の選択に当たっては、次の点に留意する
2 標題・見出しの付け方においては、次のような工夫をする
3 文の書き方においては、次の点に留意する
4 文書の構成に当たっては、次のような工夫をする
参考リンク:文化庁
文化庁の「「公用文作成の考え方」について(建議)」のリンクは、以下になります。
- 「「公用文作成の考え方」について(建議)」

令和4年1月7日の記事です。お役所ですし、決まりがあるのでしょうが、「2022年1月7日」に早くなって欲しいものです。
暗記が苦手な成果、西暦から和暦への変換も苦手です。
参考書籍
「「公用文作成の考え方」について(建議)」だけでも、私は参考になりましたが、さらに知りたい方には、以下の本が参考になります。
- 分かりやすい公用文の書き方 第2次改訂版 増補
- 記者ハンドブック 第14版: 新聞用字用語集
こちらは6年ぶりの大改訂です。
苦情処理という単語をなくしたい。かなり大変なんですが。
とある会社の管理部門から、社内でのクレーム報告に使う「苦情処理報告」の苦情処理を「不具合報告」とか、別の言葉に変えて欲しいとの要望がISO事務局にあったそうです。
話を聞いてみると、管理部門では、
- 「苦情処理報告」の帳票(書式)の文書名を「不具合報告」に変更するだけだろう。
という認識だったそうです。
実際に「苦情処理報告」の帳票(書式)の文書名を変更しようとすると、次のような作業が必要になります。
- 品質マニュアルに「苦情処理報告」という言葉が使われているか調べる。
- 全規定類に「苦情処理報告」という言葉が使われているか調べる。
さらに、「苦情処理報告」という単語だけでなく、「苦情を処理する」といった使われ方についても調べる必要があります。
つまり、全規定類を精査する必要が出てくるということです。
その後、ISO事務局から管理部門の依頼者には、
- 「苦情処理報告」の帳票(書式)の文書名を「不具合報告」にすることは、品質マニュアルと関連規定のすべてに影響があること
を説明して、改訂作業をやるかどうかはうやむやにしたとのことです。

後日、その後の経過について聞いてみると、依頼内容についてはISO規定類の維持管理を担当して間もなく気づいたが、改訂しようとすると影響範囲が広範囲であることと、作業ボリュームも大きいため見送ったとのことでした。
まとめ
品質マニュアルや関連規定を作ったり見直したりする時に、章立てや書式、文言の使い方や表記ゆれに悩むことがあります。
実際、品質マニュアルと関連規定の維持管理をしていると、中身ではなく体裁について気になることが出てきます。
例えば、表記ゆれ、気になると肝心のマニュアルや規定等の作成が中断します。かといって無視すると、形になってから後悔することになります。
ここでは、実際に使える参考資料として、お役所ですが文化庁の「「公用文作成の考え方」について(建議)」について、以下の項目で説明しました。
- 品質マニュアルや規定類の書式や文書としての整合性
- 認証取得前後
- 3年後(1回目の更新審査後)
- 「「公用文作成の考え方」について(建議)」について
- 「公用文作成の考え方」について(建議)」の目次
- 参考リンク:文化庁
- 参考書籍
- 苦情処理という単語をなくしたい。かなり大変なんですが。