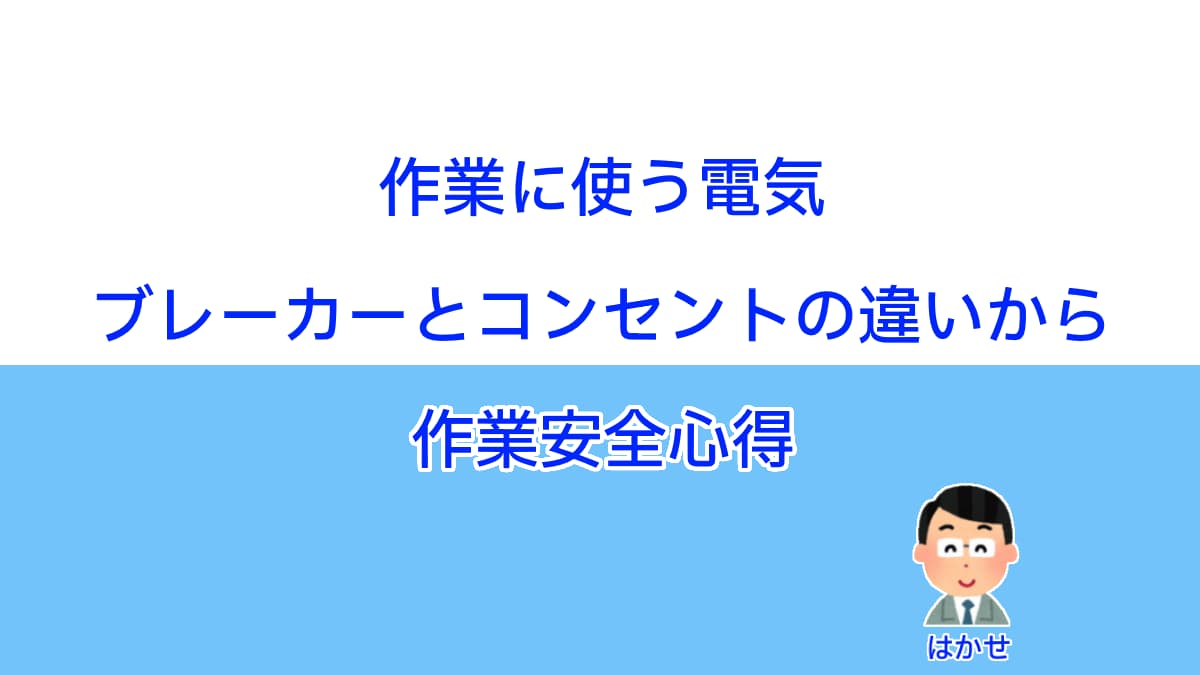最近は、義務教育でも実験の機会は少なく、工学部の研究室でも実験を経験する機会は少なくなっています。
私の場合は、振動制御を専攻した結果、シミュレーション(CAE)と実験の両方を経験することになり、実験とシミュレーションの結果が違った場合には、シミュレーションの解析条件をチェックしていました。
ところが2000年代になると、実験とシミュレーションの結果が違った場合に、「シミュレーションは正しい。実験に何かミスがあったのでは?」と考える学生さんが普通であり、驚いたことを思い出します。
モノづくりの会社に入社する人は、何らかのモノづくりの経験があるとは限りません。何らかのモノづくりを見たり体験したりしている人も少ないのが現実の様です。
入社後の教育・訓練では、安全管理や品質管理について説明をすることになるわけですが、モノづくりの作業についてイメージもなければ、モノづくりに関する言葉も知らないため、一体何から説明しなければいけないか戸惑うことも少なくありません。
このブログの品質マニュアルや関連規定は、20名規模のモノづくりメーカーを想定して作ったものですが、モノづくりの工程(様々な作業)について学ぶ前に、安全に作業するために必要な基本的な知識があります。
ここでは、工場での作業安全は、実際の作業をする人はもちろんですが、作業エリアに行く作業者以外の方にも必要なことについて、家庭の電気と作業に使う電気、ブレーカーとコンセントなどについて説明します。
家庭の電気と工場(事業所)の電気
電気は家庭でも様々な用途で使われています。工場(事業所)でも同様です。
家庭と工場(事業所)の電源は違いを列挙します。
- 家庭用は100V交流のみ、たまの200Vは大型エアコンやIHなどの調理器具ぐらいで、つまり専用コンセントを使っています。
- 工場では、電源の種類は、100V交流に加え、工作機械や設備のために200V交流とか3層交流(電源ケーブルが、赤、黒、白の3本)、高圧の電源が使われています。
- 電源の流れを見ていくと、外から工場に引き込まれた電源は、メインの配電盤に入り、そこから設備や工作機械などに分かれていきます。機械ごとに専用ブレーカーを設置している場合もあります。
機械の電気:ボール盤を例に
工場で直接電気を扱う作業は電気工事ぐらいだと思いますが、電気を使っている作業は様々です。むしろ、電気を使っていない作業の方珍しいかもしれません。
例えば、ボール盤がある場合、作業エリアにはボール盤用の電源がきており、作業エリアのブレーカーを入れないとボール盤のスイッチを押しても使えません。
では、ブレーカーを入れてボール盤のスイッチをONにします。
まだ、ボール盤は動きません。
使ったことがあれば分かると思いますが、ボール盤のハンドルを回すとドリルが回転し下がります。
これは、ボール盤の電源を入れただけではドリルが回らない、安全装置としての機能です。
また、工場ではまず見かけませんが、事務所などでパソコンの電源ケーブルが通路側に出ていて、気づかなかった人が足をひっかけて電源が抜けてしまい、パソコン作業中のデータが消えてしまったという失敗談を聞いたことがありませんか?
パソコンで作業をしていた人が、パソコンの電源ケーブルが通路側に飛び出ているのに気づかなかったために、たまたまそこを通りかかった人がケーブルに気づかず足を引っ掛けてしまう。
パソコンの作業データが消えただけなら不幸中の幸いで、足を引っ掛けた人が転倒してケガをする可能性もあります。
ドラム型の電源ケーブルを例に
もう1つ電源についての注意事例として、ドラム型の電源ケーブルの例を紹介します。
ドライヤーなどの熱を発する電気製品は、電源ケーブルの発熱も大きくなります。ドラム型の電源ケーブルを巻いたまま長期間使用していると、ドラムの内側に巻いてある電源ケーブルの発熱により、電源ケーブルの被覆が溶けてしまい、そのまま気づかないとショートするだけでなく、発火して火災になることがあります。
私も作業場のジェットヒータの電源用に使っていたドラム型の電源ケーブルが溶けた現物を見たことがありますが、ドラムに巻いてある表側の電源ケーブルはきれいなままでした。
ドラムの電源ケーブルを巻いたまま使っていると溶けてしまうという話は聞いていましたが、百聞は一見に如かずの言葉通り、実際に見て危険性を肌で感じることができました。
ドラム型の電源ケーブルで発熱するなら、いわゆる延長コードも同様です。電源ケーブルは伸ばして使うのが基本です。
電源ケーブルとホコリ
電源の配線については、ホコリも大敵です。
ACタップを機材の影や後ろに放置していると、ホコリがプラグ部分に積もっているのに気づかず、ショートや発火したりします。
見えない所にACタップを置くのは、隠すのと同じことになるので、隠さずに定位置を決めます。
例えば、ドラムを置く位置、タップを置く位置を見える場所に置いて、機材使用前に点検する。
また、使用前点検は、事故防止や安全のための有効な手段でもあります。

工場(事業所)での電気の取り扱いを間違えると、大きなケガや事故につながることを説明したかったのですが・・・。
分かりやすいとは言えない文章になってしまい力不足で申し訳ありません。
まとめ
このブログの品質マニュアルや関連規定は、20名規模のモノづくりメーカーを想定して作ったものですが、モノづくりの工程(様々な作業)について学ぶ前に、安全に作業するために必要な基本的な知識があります。
ここでは、工場での作業安全は、実際の作業をする人はもちろんですが、作業エリアに行く作業者以外の方にも必要な内容について、家庭の電気と作業に使う電気、ブレーカーとコンセントなどについて以下の項目で説明しました。
- 家庭の電気と工場(事業所)の電気
- 機械の電気:ボール盤を例に
- ドラム型の電源ケーブルを例に
- 電源ケーブルとホコリ